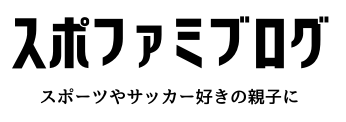サッカーの試合を見ていて、「キーパーがボールを持ちすぎて笛を吹かれた!」なんてシーンを見たことはありませんか? 実は、ゴールキーパーには「8秒以内にボールを離さなければならない」というルールがあるんです。
この記事では、サッカー初心者でも分かるように「8秒ルール」の意味・理由・よくある誤解・実際の運用について、わかりやすく解説します。
【結論】今は6秒?8秒?
最新のルール改正により、キーパーがボールを保持できる時間は「原則8秒」へと変更されています。
-
変更の理由:
「6秒」では短すぎて急いで蹴ってしまうことが多く、現代サッカーのビルドアップ(攻撃の組み立て)を阻害しないためです。 -
小学生(ジュニア)への適用:
JFA(日本サッカー協会)の規則改正に伴い、ジュニア年代でも順次「8秒」がスタンダードになっています。
※大会規定や地域によっては旧ルールのままの場合もあるため、試合前の確認が確実です。
💡 子供へのアドバイス
ルールは8秒になりましたが、審判のカウント感覚には個人差があります。
ギリギリを攻めると反則を取られるため、「心の中では6秒数えたら蹴る」くらいの余裕を持つよう伝えましょう。
8秒ルールとは?
8秒ルールとは、ゴールキーパーが手でボールを保持できる時間の上限を定めたルールです。 正式には、国際サッカー評議会(IFAB)が定める競技規則第12条「ファウルと不正行為」の中で以下のように書かれています。
ゴールキーパーは、ボールを手または腕でコントロールしてから8秒以内にボールを放す必要がある。
— IFAB サッカー競技規則 第12条より
つまり、キャッチしてから8秒を超えてボールを持っていると反則になります。 このルールは、試合のテンポを保つために設けられています。
なぜ8秒なの?ルールができた背景
かつて、キーパーはかなり長い時間ボールを保持することができました。 しかし、時間稼ぎが頻発し、試合のテンポが悪くなることが問題に。 そのため、1990年代に「6秒ルール」として導入され、現在は実質的に「約8秒ルール」として運用されています。
厳密には「6秒」と表現されることもありますが、レフェリーは時計を持って計るわけではないため、実際の運用ではおおよそ8秒程度の目安として判断されています。
8秒ルール違反をするとどうなる?
キーパーが8秒を超えてボールを離さなかった場合、レフェリーは間接フリーキックを相手チームに与えます。 これはゴール前で起きると非常に危険なシーンになります。
- 違反があった地点(だいたいペナルティエリア内)から間接フリーキック
- 壁を作ることは可能だが、距離は9.15m(10ヤード)必要
- 再三の遅延行為があれば「イエローカード」も出ることがある
とはいえ、実際にはこの反則を取られることは非常に稀です。 審判は「意図的な時間稼ぎ」や「明らかにプレー再開を遅らせた場合」に限って笛を吹きます。
よくある誤解と実際の運用
ここで多くの人が勘違いしやすいポイントを整理しましょう👇
- 「キャッチした瞬間」から数える → ✅ 正解。キーパーが手でコントロールした瞬間からカウントされます。
- 「ドリブルや転がして持ち直す」はリセットされない → ❌ 間違い。手から離さない限り、時間は継続中です。
- 味方へのパス後に再びキャッチ」は別ルール(バックパス禁止) → ⚠️ 別の反則扱いとなります。
つまり、「転がして数秒稼ぐ」などの行為は審判によっては遅延行為と判断される可能性があります。 選手も観客も「体感ではかなり長いな」と感じるタイミングが、審判にとっての“笛のサイン”なのです。
世界やJリーグでの実際のシーン
8秒ルールが実際に取られるのはかなり珍しいですが、いくつか有名な事例があります。
- 2013年 UEFA U-21選手権: イングランドのGKが8秒保持を取られ、間接FKから失点。
- Jリーグでも稀に発生: 特に終盤の時間稼ぎで審判が厳しく見ることがある。
つまり、普段は見逃されがちなルールでも、「意図的な時間稼ぎ」と見られた瞬間に一発で反則になる可能性があるわけです。
GKが意識すべきポイント
- キャッチ後は素早く状況を確認し、パスやスローに移る
- ボールを持ったまま味方に指示を出しすぎない
- 相手がプレッシャーをかけてきた場合も冷静に判断
現代サッカーでは、GKにも「テンポよく攻撃をつくるスキル」が求められます。 単に止めるだけでなく、「攻撃の起点になる」ことが評価される時代です。
まとめ:「8秒ルール」は試合を面白くするためのルール
8秒ルールは、キーパーを縛るためのものではなく、サッカーのテンポと公平性を守るためのルールです。 テンポを止めず、両チームがフェアに戦うための仕組みなんですね。
- ゴールキーパーはボールを手で持てるのは約8秒
- 超えると間接FKの対象になる
- 実際には“意図的な遅延行為”がなければ取られにくい
観戦の際には、GKのプレー時間にも注目してみてください。 「今、8秒超えたんじゃない?」と気づいたら、あなたはもう“サッカー観戦上級者”です。