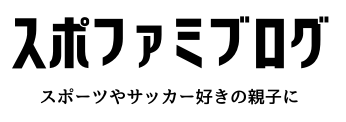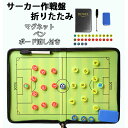「オフサイド」って難しい…。サッカーを始めたばかりの子どもや、保護者の方が一度はつまずくルールですよね。
この記事では、小学生や初心者でも理解できるように、オフサイドの意味・仕組み・審判の判断基準をわかりやすく解説します。親子で一緒にルールを学びましょう!
オフサイドとは?簡単に言うと「抜け駆け禁止ルール」
オフサイドとは、攻撃側の選手が相手ゴールに近すぎる位置でパスを受ける反則のことです。
サッカーの世界では「抜け駆け禁止ルール」とも呼ばれます。
このルールは、守備の裏で待っているだけの「ずるい攻撃」を防ぎ、フェアな攻防を生むために作られました。
オフサイドが成立する3つの条件
以下の3つが揃うと「オフサイド」と判断されます。
- パスが出された瞬間に、攻撃選手がボールより前にいる
- 相手守備選手が2人(GKを含む)より前にいない
- その位置でプレーに関与している
つまり、ゴールキーパー以外の守備が1人しかいない状態で、攻撃選手が裏に抜けてパスを受けるとオフサイドになります。
ディフェンスラインを越えた位置でパスを受けるとオフサイド。
ただし、ボールより後ろから走り込む場合はセーフです。
審判が旗を上げるタイミングと判断基準
副審(ラインズマン)は、パスが出た瞬間に攻撃側選手の位置を確認し、オフサイドであれば旗を上げます。
しかし、すぐにプレーに関与しなければオフサイドは取られません。
たとえば、パスが別の選手に渡った場合や、オフサイド位置の選手がボールに触れなければ、反則にはなりません。
小学生の試合ではどう扱われる?
小学生の試合では、審判が「明らかにゴール前で待ち構えている」と判断したときのみオフサイドを取るケースがほとんどです。
試合をスムーズに進める目的もあるため、細かい判定よりも“意識付け”が重視されています。
よくある勘違い3つ
- 自陣でボールを受けたときはオフサイドにならない
- ゴールキック・スローイン・コーナーキックではオフサイドなし
- 守備選手が触ったあとに受けた場合はオフサイドではない
特に「自陣から走り出した場合はOK」という点を覚えておくと混乱しません。
映像で学ぶともっとわかりやすい!
オフサイドは文章だけではイメージがつきにくいルールです。
YouTubeなどのハイライト動画を一時停止しながら、「今のプレーはオフサイド?」と一緒に考えると、子どももすぐに理解できます。
また、家庭用の戦術ボードを使ってコマを動かしながら説明するのもおすすめです。
親が子どもに教えるときのコツ
「ディフェンスより前にいないようにしよう」とシンプルに伝えるのがコツです。
難しい言葉よりも、実際に映像を見せながら感覚で覚える方が効果的です。
また、子どもがミスしても「惜しい!もう少し後ろから出よう」とポジティブに声かけすることで、プレッシャーなく学べます。
応用編:オフサイドトラップとは?
ディフェンス側が意図的にラインを上げて、相手をオフサイドにさせる戦術を「オフサイドトラップ」といいます。
小学生には少し難しいですが、中学年代になるとこの戦術が重要になります。
ただし、タイミングがずれると一気に裏を取られてしまうため、チーム全体で連携することが大切です。
まとめ
- オフサイド=抜け駆け禁止ルール
- 成立には「パスの瞬間」と「位置関係」が重要
- 小学生試合では意識づけが中心
- 映像を使うと理解が早い
オフサイドは最初は難しく感じますが、見慣れると自然に判断できるようになります。
ぜひ、親子で一緒に試合を見ながら「今のプレーはオフサイド?」と考えてみましょう。
関連記事
- 【サッカー解説】キーパーの「8秒ルール」って何?知られざるゴールキーパーの制限時間
- 【初心者向け】サッカースパイクのお手入れ方法|簡単な手順を解説
- 初めてのサッカー親子も分かる!VAR判定とは?使い方や流れを解説